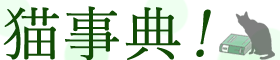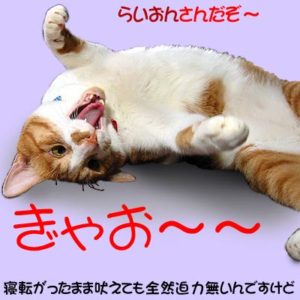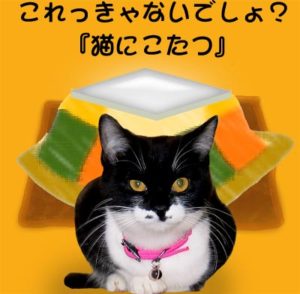獅子も頭の使いがら
ししもかしらのつかいがら
【意味】
神楽の獅子舞も頭の部分を振る人の上手下手で善し悪しが決まるの意から、人は、先頭に立つ者の使い方で、どのようにでも働くものだということ。
指導者の働きが重要であることのたとえ。
【参考文献】
『成語林』旺文社、『広辞苑』岩波書店、『大漢語林』大修館書店、『四字熟語の辞典』三省堂、ほか。参考文献の全リストはこちら
【猫的解釈】

【雑学】
日本語で“しし”といえば
日本語で、動物関連で「しし」という音にはつぎのような意味もある。
- 肉・宍
肉、特に、食用の獣肉のこと。 - 獣・猪・鹿
肉という意味の「しし」から転じて、獣、野獣の意。 特に食肉のために捕獲する“いのしし”(猪)、“かのしし”(鹿)のこと。 - 尿
幼児語で、尿のこと。 - 獅子・師子
(1)ライオン。からしし。
(2)左右の狛犬のうち、向かって右方の、口を開いた方。
(3)獅子頭の略。
(4)舞楽の一つ。唐楽。
(5)能の舞事の一つ。
獅子舞とは

- 獅子頭をかぶって行う舞。 唐から伝わり、舞楽として演奏したが、後に変容して太神楽や各地の祭礼などで、五穀豊穣の祈祷や悪魔払いとして、新年の祝いに行われるようになった。
- 能の舞事。