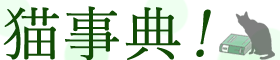結構毛だらけ猫灰だらけ
けっこうけだらけねこはいだらけ
「たいへん結構だ」の意をふざけていうしゃれ言葉、地口。
昔は、寒い季節、かまどの火が消されたあとも灰はあたたかく、猫がかまどの周りや、ときには灰の中に潜り込んで暖を取るというのはごく普通にあった光景でした。そのため俳句にも「竈猫(かまどねこ)」「灰猫」「へっつい猫」等が冬の季語としてあります。

宮沢賢治の童話『猫の事務所』に出てくる竈猫
軽便鉄道の停車場のちかくに、猫の第六事務所がありました。・・・と始まる短編です。なお、ここでは、「竈猫」と書いて「かまねこ」と読ませています。
事務長は大きな黒猫。その部下の、一番書記は白猫、二番書記は虎猫、三番書記は三毛猫、そして、四番書記が、竈猫(かまねこ)です。
竈猫というのは、これは生まれ付きではありません。生まれ付きは何猫でもいいのですが、夜かまどの中にはいってねむる癖があるために、いつでもからだが煤できたなく、殊に鼻と耳にまっくろにすみがついて、何だか狸のような猫のことを云うのです。
ですからかま猫はほかの猫には嫌われます。
最初は事務長の黒猫だけはかばってくれました。ところが、かま猫が風邪で休んだ翌日から、事務長さえ、かま猫をいじめるようになってしまいます。短い童話ながら読んだ後に心にシインと沈む何かが残ってしまう、そんな名作です。
季語「竈猫」「灰猫」「へっつい猫」関連の俳句例
以下、すべて『俳句・短歌・川柳と共に味わう 猫の国語辞典』(佛渕健悟・小暮正子編)からの引用になります。猫好きなら買わなきゃ損のすごい本です。詳細は↓
「竈猫」かまどねこ
竈のそばで暖をとる猫。竈は冬場の猫が好む場所。
- 荒神(こうじん)は瞬きたまひ竈猫(飯田蛇忽)荒神=かまどの神。火影がちらちら
- しらたへの鞠のごとくに竈猫(飯田蛇忽)白猫が丸くなっている
- 容色をふかめてねむるかまど猫(飯田蛇忽)容色=美貌
- ガンジーの死を汁寺の竈猫(萩原麦草)
- 浜往くにだまりこくりて竈猫(萩原麦草)
- 新嫁の来るとも知らず竈猫(赤星水竹居)
- 竈から猫の見ている亥子哉(いのこかな)(正岡子規)亥の子の祝い=秋の収穫祭
- 寒食(かんじき)や竈下(そうか)に猫の目を怪しむ (其角:~江戸時代)寒食(火を使わない冷たいものを食べる風習)の日に猫の目が妖しく光る
- 釜の神鳴仔やかぐらの増えの役(言水:~江戸時代)釜の神=かまどを守る神
「灰猫」はいねこ
(1)灰色の猫。(2)火を落としたかまどの中に入って暖を取り、灰だらけになった猫。かまど猫。
- 灰かきに掘出されけり猫の夫(つま)(広江八重桜)
- 灰猫のやうな柳もお花かな(一茶)
- 灰猫の妻こふ声やかまびすし(正彌:~江戸時代)かまびすし=やかましい、騒がしい
- 帰り来て灰にもいねず猫の妻(太祇:~江戸時代)いねず=寝ず
- 釜の下に住つけたりし灰猫の目が光るかとみれば埋火(うずみび)(江戸狂歌)埋火=灰に埋めた火
へっつい猫(竈猫)
かまどで暖を取る猫。冬の季語。
- 恋猫の妻も籠れり竈(へつい)の下(内藤鳴雪)へっつい=かまど
- 猫の妻竈(へつい)の崩れより通ひけり(桃青(=芭蕉))
- へつつゐやけぶりくらべて猫の妻(松遊:~江戸時代)へっついの灰の汚れと恋猫としての汚れとどっちが汚いのだろう
※ところで、「へっつい+猫」といえば、もうひとつ思い出さずにはいられないものがあります。夏目漱石『吾輩は猫である』のモデルとなった猫です。その猫が死んだとき、漱石は親しい弟子たちに「猫の死亡通知」を出しました。それによると、猫はへっついの上でひっそりと亡くなったのでした。詳細は以下をご覧ください。

文例
映画「男はつらいよ」
寅さん(渥美清)の口上。
結構毛だらけ猫灰だらけ、お尻の周りはクソだらけってねぇ。タコはイボイボ、ニワトリゃハタチ、イモ虫ゃ十九で嫁に行くときた。