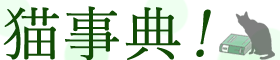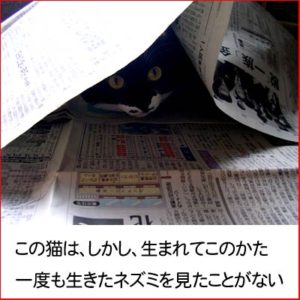猫の目/猫の目のよう
ねこのめ
ねこのめのよう
【意味】
猫の目が明暗により細くなったり丸くなったりすることから、 物事がめまぐるしく変化しやすいことのたとえ。

【類】
*同じ意味ではないが似たような諺
女の心は猫の眼 おんなのこころはねこのめ
–
【参考文献】
『成語林』旺文社、『広辞苑』岩波書店、『大漢語林』大修館書店、『四字熟語の辞典』三省堂、ほか。参考文献の全リストはこちら
【猫的解釈】






*ねこの目、こちらにもあります。
【雑学】
猫の目と視力について
●ネコの眼はヒトの眼よりわずかに小さいが、 瞳孔の面積はヒトの3倍以上に拡大できる。
●ネコの眼にはタペタム(輝板)と呼ばれる、 光を反射する機構が備わっていて、 明暗情報を約40%増加させることができる。
●ネコの眼には、光を感じる桿状体細胞(かんじょうたいさいぼう) はヒトの3倍以上もあるが、色を感じる錐状体細胞 (すいじょうたいさいぼう)はヒトの5分の1しかない。
● ヒトの錐状体細胞には、それぞれ、赤・緑・青を感じられる 3種類の細胞があるが、ネコはそのうち、赤を感じる細胞を 欠いていると考えられている。 そのため、ネコが識別できる色は黄色から青色までの範囲であり、 赤色は黒っぽく見えていると思われる。
猫の目で時間を知る?
昔、猫の瞳は明るさではなく、時刻によって変化すると考えられたことがあった。
古くは北宋の蘇東坡(1101年没)が『物類相感志』の中で「猫児の眼、時を知る」と書いている。
その間違った思想は日本にも伝わり、一部信じられた。 猫の目を表した古歌が今も伝わっている。
・ 六つ丸く 五七卵に 四つ八つは 柿の核なり 九つは針
・ 六つ丸く 四八瓜ざね 五と七と たまごなりにて 九つは針
いずれも、時刻により猫の眼の形が「針」から「卵」まで変化する様子を歌っている。
*こちらのページでもう少し詳しく紹介しています。よろしければどうぞ。
【猫の目:文例】
村上春樹『羊をめぐる冒険』
「・・・一応わかっているだけの緬羊業者の住所は三十ばかり控えてきたけれど、これは四年前の資料だし、四年のあいだには結構移動があるらしいわ。日本の農業政策は三年ごとに猫の目みたいに変化しているから」
講談社文庫(下)p.30
「やれやれ」と僕は一人でビールを飲みながらため息をついた。