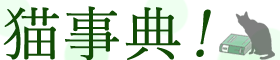管豹の一斑
かんぴょうのいっぱん
【意味】
管の中からヒョウを覗いて、そのまだら模様の一部分だけを見るという意味で、ものの見方や見識がたいそう狭いことのたとえ。
【類】
管を以て天を窺う かんをもっててんをうかがう
管窺蠡測量 かんきれいそく
井に坐して天を観る いにざしててんをみる
井中星を視る せいちゅうほしをみる
針の穴から天を覗く はりのあなからてんをのぞく
葦の髄から天井を覗く よしのずいからてんじょうをのぞく
【参考文献】
『成語林』旺文社、『広辞苑』岩波書店、『大漢語林』大修館書店、『四字熟語の辞典』三省堂、ほか。参考文献の全リストはこちら
【猫的解釈】

【雑学】
出典
『晋書しんじょ』王献之伝おうけんしでん
ヒトは色が見えていない
“三原色”という言葉は聞いたことがあると思う。
一般的には、“光の三原色”なら赤・緑・青、“色の三原色”なら青・赤・黄色。 ヒトの目に見える色は、すべて、この三原色の組み合わせで表現できる。
では、ヒト以外の生物も同じ三原色で見ているのだろうか?
猫は、二原色で世界を見ている。 そして鳥類は、なんと、四原色の世界に生きている。 鳥には人間には見えない紫外線も見える。
残念ながら、鳥の目に色がどのように映っているか、ヒトである我々にはわからない。 ただ、我々より遙かに色鮮やかな世界だろうことは確かだ。
実は哺乳類も、爬虫類も、恐竜たちも、昔は皆、四原色だったそうだ。 ところが、哺乳類は夜行性になった時点で二原色を失ってしまった。
その後、サルなど一部の哺乳類が、三つめの色を再び認識しはじめた。 しかしまだ進化途中なので不完全なのである。
鳥は、見える四つの原色の波長がきれいに四つの山を作る。 そのため、この世界に存在する色が(多分)まんべんなく全て見えている。
ところがサル科の見る三原色は不完全で、波長の山がかなり重なってしまっている(まだ完全分離していないと表現すべきか)。 そのため、色も一部しか見えていない。
我々ヒトも、不完全な三原色で見ているサルの一種にすぎないのである。
鳥から見れば、ヒトなんて、ヒョウの全身をくまなく見てさえ
「何も見えてないじゃん(爆笑)」
のレベルかもしれない。

ヒョウの毛皮は国際取引禁止
ワシントン条約は、正式には 「絶滅の恐れのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」 という。 1973年にワシントンで採択され、世界の約170カ国が加盟している。 (日本の批准は1980年)。
この条約の目的は、国際取引を規制することで絶滅が危惧されている野生動植物を保護すること。 その規制対象は、生体だけでなく、毛皮、皮革製品や漢方薬等も含まれる。
規制対象となる動植物は次の3つに分けられる。
【附属書 I 】
絶滅の恐れのある種で、国際取引による影響を受けているか、 受けることのある種。商業目的の国際取引は禁止。
【附属書 II 】
国際取引を規制しないと絶滅のおそれのある種。 取引には、輸出国政府の管理当局が発行する輸出許可書を必要とする。
【附属書 III 】
ワシントン条約の締約国が、自国内の動植物を保護するため、他の締約国の協力を必要としている種。 取引には輸出国政府の管理当局が発行する輸出許可書又は原産地証明書が必要。
ヒョウは、【附属書Ⅰ】である(2008.2.8.現在)。
一般人は、生きたヒョウはもちろん、ヒョウの毛皮や、 ヒョウ爪のアクセサリー、ヒョウの漢方薬などを日本に持ち込むことはできない。
ヒョウの毛皮を居間に飾るなんていうのは、今や 「私は見識の狭い人間です」と公言するも同然な行為といえよう。
なお、ネコ科 Felidae は、イエネコ種を除き、すべての種が【附属書Ⅰ】または【附属書Ⅱ】。